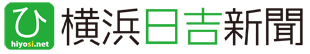「命の危険」から身を守るための交通安全教室が好評を博しています。今週(2019年)6月26日の午前、新吉田小学校(新吉田東6)で、港北区内の全25小学校で開催されている、2019年度「はまっ子交通あんぜん教室」が、同小の1年生と4年生を対象に行われました。
この日の天候は晴れ。夏を思わせる暑さの中、港北警察署や港北区役所のほか、横浜F・マリノス(横浜マリノス株式会社・新横浜2)からトリコロールマーメイズ、港北区安全安心大使も務めるマリノスケ、PTAなど児童の約30人の保護者らが参加しました。
港北警察署の担当者らによる「安全な歩き方教室」や、トラックやバスの車体を使っての「死角」や「巻き込み」、「制動」や「衝突」実験も。
トラックやバスなど、特に大型車における内輪差の危険性については、実際に車両を運転しての実例を眼前に示すことで、児童に「命の危険」を訴えていました。
東急バスによる実演では、バス停前後の飛び出しの危険性や、急ブレーキにより乗車している人が数メートルも飛ばされる様子を披露、児童や保護者からの大きな驚きの声があがっていました。
今回のバスの実演を指揮・監督した東急バス新羽営業所(新羽町)の花井誠所長は、「小学生がバスの前に飛び出して、やむなく急ブレーキをかけたことから、乗車していた人がケガをして病院に搬送されたという事故が、この地区でも(2年ほど前に)ありました。もし自分の家族がケガをしたら、という視点で、くれぐれも(道路やバスの前後では)飛び出さないように注意してもらえれば」と、バスを利用する人が多い新吉田小学校の周辺環境にも言及し、注意を喚起します。
同校に東急バスが登場するのは、昨年度の実施以来2回目、また港北区内でも、2017年秋以降通算でも今回が5回目といった数少ない機会となっていることから、「このように実際に“見て”リアルに学べることが、大変ありがたい」(同校PTA役員)と、実際にバス車両を眼前にしての、実体験に基づいた交通安全教室の有効性について言及します。

トラックの死角を学ぶシーン。周囲に児童(とマリノスケ)が立っても、運転席からは前方と後方の人の頭しか見えない。しゃがんでしまうと全く見えなくなってしまう。「車の周りでは遊ばないように」と、港北署・交通課の堀井健さん
昨年(2019年)同校に赴任し今年で2年目となった藤城守校長は、2020年度に全面実施される予定の新学習指導要領について、現在指導内容の見直し作業をすすめているところだといい、特に “新田中ブロック”(新田中学校に進学する予定の児童が在籍する新吉田小学校、綱島小学校、新吉田第二小学校、新田小学校の4校)では、主体的・対話的で深い学び(アクティブ・ラーニング)の視点から、「自分づくり」に視点を置いての教育活動を行っていく方針とのこと。
「子どもたちが、しっかりと教育活動の中で夢を持ち、“自分をつくる”力をいかに育むか、それには、『人との出会い』こそが大切なのです。警察、バス会社、マリノス、そして区役所の皆さんとの出会いを通じて、交通安全はもちろん、“こうなりたい”という目標を持って物事に取り組んでもらえるようになれば」と、交通安全のみならず、今回の教室から得られる様々な学びのメリットについて説明します。
初めて港北区内のこの教室の場に立ち会った、東急バス株式会社(東京都目黒区)の山口哲夫社長は、「バス会社が地域の学校に積極的に出ていくことで、交通安全をより学んでもらえるきっかけにしてもらえれば。地域貢献を行うべく、東急沿線のグループ企業としての役割を果たすのはもちろん、将来、バス会社で活躍してくれる子どもたちとの貴重な出会いの機会にもなれば」と、東急沿線地域の学校での、安全啓発活動の意義について熱く語ります。
特に横浜市内では、昨年(2018年)10月に西区での路線バスによる死傷事故が大きく報道され、東急バスでも、同12月に、東京都世田谷区内で小学生の死亡事故が発生しています。
なお、区内での「はまっ子交通あんぜん教室」は、今年は夏休みまでの間には、ほとんどの学校で実施(秋に開催は1校のみ)される見込みとのこと。
東急バスの車両が入れる学校は限定されており、これまでに、同バス路線エリアの下田小学校(下田町4)、綱島小学校(綱島西3)、そして新吉田小学校でのみ実施されています。
【関連記事】
・東急バスが校庭に初登場で危険を体感、下田小で開催の交通安全教室に歓声と驚き(2017年11月6日)※「はまっ子交通あんぜん教室」に東急バスが初登場
・グリーンサラウンドや新吉田東を結ぶ「綱74系統」で増発、道路の狭さに苦慮(2019年6月24日)
【参考リンク】
・児童・幼児の交通安全対策(横浜市港北区)*はまっ子交通あんぜん教室について