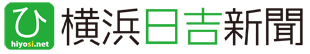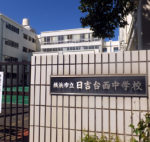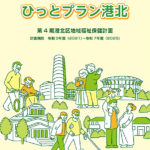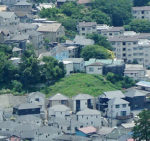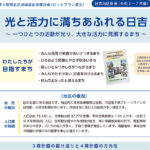オール日吉の「まちづくり」イベントが10回目の開催となりました。日吉地区社会福祉協議会(片野芳昭会長)は、日吉地区での活動発表や情報共有を目的とした「福祉実践活動発表会~光と活力」を、きのう(2019年1月)27日(日)午後に、慶應義塾大学日吉キャンパス(日吉4)協生館内の藤原洋記念ホールで開催しました。
当日は、日吉エリアの自治会・町内会関係者や福祉施設、民生委員などで組織した同社会福祉協議会が、2016(平成28)年度から5年間にわたり行っている「第3期地域福祉保健計画」(ひっとプラン港北)で掲げている「防災から福祉を考える」との共通テーマで行ってきた「町あるき」の成果としての防災マップづくりの進捗状況を、エリアごとに報告。
今回は、日吉本町、宮前、日吉町、箕輪、下田の5つの地区の活動報告のほか、「防災町あるきフォーラム」としてのパネルディスカッションも行われました。
防災マップは、ひっとプラン港北(第3期)が終了する2020年度までの完成を目指しており、昨年6月に発生した大阪府北部での地震でも指摘されたブロック塀の危険箇所や、周辺河川の水害時の「いっとき避難所」、AEDの設置箇所などについても情報共有するためのマップ完成に向けての決意を新たに共有する機会となりました。
これからさらに人口が激増することが予想される日吉・綱島エリアに位置することもあり、日吉地区連合町内会の小島清会長(箕輪町町内会会長)は、箕輪町2丁目の旧アピタ日吉店など一連の跡地で行われている「プラウドシティ日吉」(野村不動産)の大規模再開発に伴う人口増への対応についても言及。
「これから箕輪町に新小学校(箕輪小学校:箕輪町2)も2020年4月に開校が予定され、消防団員や民生委員といった町に関わる担い手も必要になる。5、6年かけて最終的には人口が約4000人も増えていく段階の中で、地域として一緒に助け合いながら活動していければ」との考えを示しました。
また、箕輪小学校の学区に綱島地区も含まれることから、まちづくりの“運営方法”の綱島エリアとの違いについても、さらなる議論や決定事項が必要になるとも指摘しました。
今回のフォーラムでは、ボランティア活動の募集や災害時の連絡手段について、SNSやインターネットの活用については言及されず、電話や、公共の場所などに設置している掲示版を利用するとの発言に留まりました。
各地区における日々の福祉現場や、防災の活動現場での担い手不足の問題は切実で、若年層の地域活動への参加をいかに促していくのかも今後の大きな課題となりそうです。
【参考リンク】