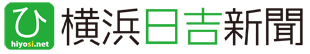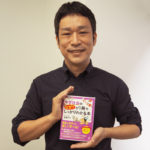【法人サポーター会員による提供記事です】4月もはや後半。ゴールデンウィークも近づき、心浮き立つ家庭がある一方で、新学期からの新しい環境に慣れず、親子共々「ブルー」になってしまう人も多く見受けられる季節になりました。
保育園や幼稚園、学校や「塾」、習い事、そして学童などに子どもをとりあえず預ければ、全てが解決すると思ってしまうと思ってしまうのも、親心。
時に、高額な費用を出してまで子どもを預ける「学習塾」にどこまで親は頼れるのでしょうか。
日吉駅から徒歩約3分、日吉中央通りで子どもたちを迎え入れている学習塾「ひよし塾」(日吉本町1)塾長の玉田久文(ひさあき)さん(株式会社タマダ代表取締役)に、新学期にあたり注意すべき子どもとの接し方や、学習塾全般に子どもを預ける際に留意したいポイントについて、話を詳しく聞きました。
低学年までは鉛筆や箸の「持ち方」を正しくマスターすること
ひよし塾では、同塾で開催している「習字教室」や「パズル道場」に通う低学年の生徒(上級生の各教室は除く)を含むと、現在、未就学児と小学校低学年16名、高学年66名が通塾しています。
玉田さんが児童を指導するにあたり特に気になるのが「鉛筆」や「箸」の持ち方。
全体的な傾向としては、特に共働き家庭で、それぞれを“グー”で持ってしまう児童が多い傾向にあるとのことで、「指先を使うピアノなどにも当てはまりますが、正しく鉛筆や箸を持つことで、学びにも良い影響があると考えています」と、どんなに忙しい家庭でも、鉛筆や箸の持ち方については、まずは、各家庭できちんと教えてもらうことが大切と感じているといいます。
また、同塾で開催している「パズル道場」でも試みる「空間での数や量の認識」を出来ない児童も増えているといい、「教育効果を重視するあまり、子どもに、足し算や引き算など、数字で“ただ答えを出すだけ”の指導に走ってしまい、数を“量”として認識できない子どもが増えています」と玉田さん。
例えば、鉛筆の持ち方などでも、「学校では、低学年の生徒に対し教えることが多々あり、担任の先生が一人一人の持ち方の改善の確認までするには、かなりの時間がかかってしまいます」と、つい“学校まかせ”になってしまう親の無意識での錯覚にも警鐘を鳴らします。
学校行事も多く「塾にも集中できず」ペースを乱しやすい高学年
学校にも充分慣れているはずの小学校高学年も、運動会や宿泊を伴う学校行事など、大きなイベントが学校内外で重なり、7月が終わる頃までなかなか自分のペースをつかめない児童も見受けられるといいます。
「大人ですら“五月病”になりやすいこの季節。夏になっても自分のリズムをつかめないと大変です」と、新しい環境に馴染めず、大人よりももっと子どもは不安定になりやすいとのことで、「学習面においても、とにかく“塾まかせ”にせず、親が子どもの話をまずは良く聞き、一緒に物事を考えてあげることが大切です」と、高学年においても、親と子が一緒になり、学びの習慣を作りあげていくことが大切と訴えます。
親が考えを押し付けず、子どもが「自ら」学べる環境を
春先に憂鬱(ゆううつ)になるのは子どもばかりでなく、親にとっても新学期ならではの慣れない環境は辛いもの。「特に、第一子に対して、親が自分の経験を基に“こうあるべき”と、自分の価値観を押し付けてしまうのは禁物です」と、多少“伸びやかに”物事を行うことを見守る勇気も大切だと玉田さんは指摘します。
特に、親が子どもの「評論家」になってしまうケースも多く、「子どもはプロではありません。結果で求められると、子どもは委縮してしまいます。親の価値観を押し付けるのも子どもにとってはつらいものです。親は、自分の過去を持ち出す際、大概、自分を美化してしまうのです」と、何より、子どもの立場や目線に立って“一緒に考える”ことこそが大切だと訴えます。
玉田さんがひよし塾(本コース)に通う生徒向けに開設している「自習ルーム」では、ここ最近の流れでは、「前向きに学習に取り組む子どもたちが増えている」と感じているといい、「それぞれがいい影響を与え合っていける時間や産み出し、子どもが“自ら学びたい”と感じてもらえるような環境を作っています」とのこと。
まずは、同塾でも、安心して子どもたちが学習に取り組むことができる場所を提供しながら、「与えられる価値観ではなく、自ら学べる環境を作りだすことで、この時期をまずは“安心して”乗り切ってもらえるよう工夫していきたい」と、子どもをただ叱りつけ、ただ自分の価値観を押し付けるよりは、“自然に自ら”が環境に馴染む場を作る支援をしてもらいたいと訴えます。
ライバル心から来るプレッシャーは少人数教育や「体験教室」でクリア
特に、中学受験を志す子どもたちには、より競争心を煽(あお)られる新学期は、プレッシャーそのもの。
「当塾では、少人数教育のため、それぞれ子どもたちの目標校が重ならないことが多く、のんびり仲間意識を持ち、これからの人生の課題にも立ち向かっていける“心”を育ててもらいたいと思います」と、ただ机上や室内での学びに終始しがちな中学受験生に対しても、「フィールドワーク」という体験や実地での学習を通じて、一過性でない、生涯役立つ“学び”を得てもらいたいと、同塾ではプログラムを組んでいるとのこと。

フィールドワークの模様は、ひよし塾サイトの「ギャラリー」のページに詳しい
4月末にも、理科の実験教室として、三浦半島・葉山まで出向き、海の干潮時に生まれる“タイドプール”で、アメフラシやタツナミガイ、タコやウニといった海洋生物について学ぶプランを立てているとのことで、「このようなフィールドワークは、場所やテーマを変え、春から秋にかけて年間5~6回行っているんです。最近の子どもたちは、忙しい共働き家庭の増加がやはり背景にあり、“実際に体験して”学び合う経験が不足していると感じます」と、玉田さんは、中学受験塾ではあまり例をみないこの「屋外学習」にも力を入れています。
同じ体験を同じ境遇の仲間たちとするだけで「机上で学ぶプレッシャーからも解放され、“学ぶ楽しさ”を感じてもらえるんです」と、仲間作りはもちろん、“人”としての経験値を上げていけたら、と玉田さん。
「親と子で学び合う習慣作り」に何が必要か、最低限の確認を
とはいえ、塾に出来ることはやはり限られると感じるといい、「特に、学習でつまずきやすい春先に、親と子で“学習の習慣”を作ることが大切です」と訴えます。
特に、親に確認してもらいたいことは「漢字のチェックです。大人は、難しい漢字や文章も“見慣れている”ので、あまり感じませんが、子どもたちからすれば“初めてのトライ”となる漢字は、本当に難しいものなのです。一度、間違ってしまうと、反復して間違えてしまうことにもつながり、なかなか改善も難しくなるので、ぜひ、細かく見て上げてもらいたいと思っています」と指摘します。
また、算数でも、「繰り下がりの引き算に弱い生徒は、分数や少数が出でくるとついていけなくなってしまうことも多い」とのことで、「多くの低学年の児童が塾に通う前、特に、1、2年生のうちに、親が計算を見てあげるのみならず、“物の量”をリアルに数える習慣を一緒に身につけてもらえたら」と、親が子どもの勉強を見る大切さについても言及します。
“土壇場で力を発揮”しやすい地域活動をバックアップ
ただ勉強に子どもを押しこむこともプレッシャーにつながりやすい新学期ならではの取り組みとして、「地域でのスポーツや習い事など、“勉強以外”の子どもの居場所づくりも、振替受講を柔軟に行うなどして応援しています」と玉田さん。
何かを集中して行うことにより、「学校のテストや、中学入試でも大きな力を発揮する力を蓄えることができるので、課外活動には積極的に取り組んでもらいたいと考えています」と、特に同塾では、特定の運動系チームの児童が口コミで入塾してくるケースも多くあるといいます。
“土壇場で力を発揮しやすい”力を育む地域社会での活動を、これからも重視し、支援していきたいと語ります。
・・・・・
慣れない新学期を乗り切る秘訣は、「子どものみならず、親や塾、習い事の先生、そして地域社会の応援があってこそ」と訴える、玉田さんが想い描く、「塾まかせ」「学校まかせ」ではない、親も地域も一緒になった子育ての在り方。
自身もまさに子育て中で、「親にとってもつらい新学期、一緒に乗り越えていきましょう」と語る玉田さんや同塾が描く“新学期の乗り切り方”は、多く子育てに悩む親たちにとっての一つの指針となりそうです。
【関連記事】
・なぜ子どもが「パズル」に夢中になるのか、1/20(土)に日吉で新年度向け体験会(2018年1月9日)
・日吉の学習塾で「文字書く」大切さ伝える習字教室、“初めての鉛筆”体験会も(2017年12月4日)
・ひよし塾が増床で「自習スペース」も確保、共働き家庭の増加に対応(2018年2月28日)
【参考リンク】
・ひよし塾サイト(株式会社タマダ運営)
・ひよし塾へのアクセス(同社公式サイト)
(法人サポーター会員:中学受験ひよし塾~株式会社タマダ提供)