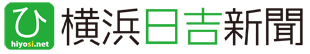“雨にも負けず”日吉駅前をきれいにしたいという想いで、7人の学生が清掃活動をおこないました。
今から3年前の2018(平成30)年10月、日吉駅西口の商店街一帯と東口駅前が横浜市内で27カ所目の「美化推進重点地区」に指定されたことを受け、同エリアでは、横浜市から任命された地域の「美化推進委員」(2021年度から港北区美化推進委員)が、毎週2回の清掃活動をおこなっています。
タバコや空き缶のポイ捨てをなくすための美化活動や啓発を行うことを目的としたこの活動に、慶應義塾大学商学部の学生が呼応。
商学部2学年に在学する野々村百華(もか)さんを中心とした7人のグループが、美化活動を推進している港北区役所(大豆戸町)の支援のもと、「美化推進委員」とともに、今年(2021年)10月から、授業内での週1回程度の清掃活動をおこなってきました。
この「総合教育・地域との対話」授業を展開するのが、経済史や経営史、産業史を研究分野としている牛島利明教授。
きのう12月13日(火)午前に日吉駅前でおこなった清掃活動には、牛島教授も参加。日吉駅のシンボル「銀玉(ぎんたま・ぎんたま)」こと「虚球自像(こきゅうじぞう)」前に集合した学生たちに、同区役所資源化推進担当の深井隆稔さんが、ごみ拾いをおこなうためのトングとごみを入れるためのビニル袋を配布した後、通算5回目となる清掃活動をスタート。
野々村さんのほか、井出侑希(ゆうき)さん、宇野嘉那子さん、前田純希(あつき)さん、高木聡一さん、岩金(いわかね)慶さん、石川真有(まゆ)さんが、“突然”降り出した冷たい雨の中、約20分間にわたり、トングを片手に、タバコの吸い殻やドリンク缶・カップなどのごみを拾いながら日吉駅周辺を歩きました。
「地域との対話」授業は、2004(平成16)年からスタートした授業で、今年度は約20人受講する中、大小グループに分かれてテーマを選定。
広島県や兵庫県、静岡県の出身者など、「地元出身でない学生が多いクラスで、現在、日吉や高田、元住吉など、近郊に在住している学生が多いことも、日吉商店街に注目し今回の活動に至った理由の一つかもしれません」と、元住吉駅から東側一帯に広がるモトスミ・オズ通り商店街(中原区)と協力しながら、地域コミュニティ形成に尽力してきた牛島教授は分析、清掃活動の実現を後押ししたとその想いを語ります。
商店街の活性化や子育て・障害者支援、地域コミュニティのあり方など地域の抱えるさまざまな問題について調査や提言を行うというこの授業にチャレンジしている野々村さんたちは、「ここが、最も汚れている場所なんです」と現地に足を運び、率先しての清掃活動をおこなっていました。
特に、街に来た人の「たまり場」と思われる場所にごみが溜まってしまうケースが多いといい、「排水溝にタバコの吸い殻が投げ捨てられてしまうことを問題視していたところ、道路を管轄する港北土木事務所(大倉山7)が、タバコが捨てられにくい蓋(ふた)に交換できるか調整してくれています」(深井さん)と、早速に一つの“問題解決”に至る成果を得られたとのこと。
「他の街よりはきれいなほう」との日吉の街の印象が学生からも聞かれたなか、「それでもごみが多い場所がある」と野々村さん。
かつて日吉の街の活性化を目的とし、慶應義塾大学の学生との交流を促進した「ヒヨシエイジ」のアドバイザーも務めた経験も持つ牛島教授は、日吉商店街についての研究論文についても指導するなど、日吉の街を最もよく知る慶應義塾大学の教授としても知られています。
「雨だったからか、いつもよりは少ないごみの量となりました」と語る野々村さん、参加した学生たちの目には、未来の日吉の街がどう映っているのか。
「通年」の授業だという取り組みの結果が、どのような果実を生むことになるのか。今後の研究成果に、どのように今回の活動が反映していくのかにも、大きな注目と期待感が寄せられていくことになりそうです。
【関連記事】
・日吉駅前の“ポイ捨て”一掃へ本腰、10月から市が「美化推進重点地区」に指定(2018年9月7日
・<美化推進地区に指定>日吉駅前での清掃活動を開始、街全体での思い共有が重要(2018年10月2日)
・ラグビーをブームで終わらせない、慶應生が小学生に楽しさ伝える出張授業(2019年11月6日)
・あす11/5(土)昼から「日吉フェスタ~ヒヨシエイジ」、ステージ発表や映画上映会も(2016年11月4日)※この年の開催を最後に、以降「ヒヨシエイジ」イベントは行われていない
【参考リンク】
・慶應義塾大学商学部 総合教育セミナー「地域との対話」(同研究室)