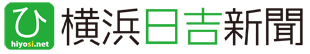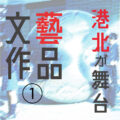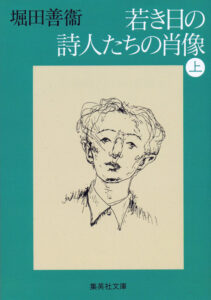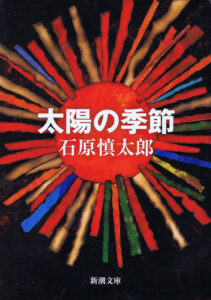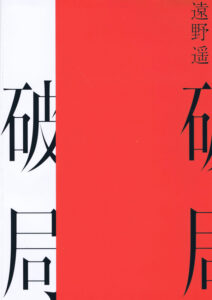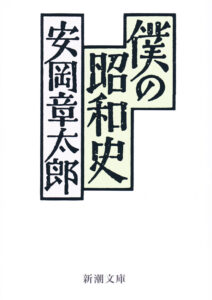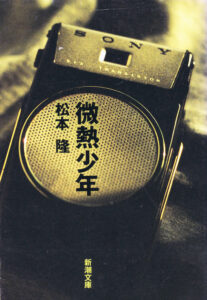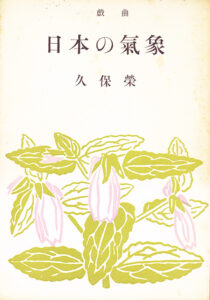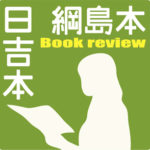港北区が登場する書籍を紹介していく連載「港北が舞台の文芸作品」。第1回は慶應義塾大学日吉キャンパスと日吉駅周辺を描いた3人の芥川賞作家の作品を中心に、戦前から現在までの風景や時代の変化を探ります。
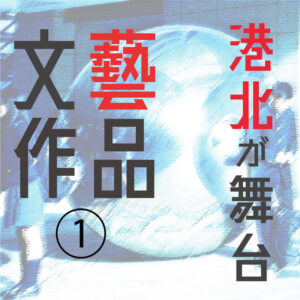
今年(2024年)で誕生から90年を迎えた慶應日吉キャンパスは、現在の大学における「一般教養課程」に似た旧制大学の「予科」校舎として1934(昭和9)年に開設されました。
そうした流れで戦後は慶應義塾高校(男子校)が設置され、大学では主に1・2年生が一般教養課程を学ぶ場という位置付けとなり、今も学内には十代後半の大学生と男子高校生が目立ちます。
次の引用は、今から80年以上前の日吉キャンパスが誕生して間もない頃、芥川賞作家が描いた教室内の様子です。
予科の教室にも迫った戦時の弾圧
そのとき、警察は教室へじかに顔を出したわけではなかったが、彼らの二人がそろって呼び出されたということは、それだけですでに事態が何であるかを物語っていた。二人の顔色は、転瞬の間に白々と、粉でも吹いたように青ざめ、眼がしらで彼らは級友のすべてに訣(わか)れを告げて行った。クラス担任のドイツ語の教師が、これも一瞬凝然と立ちすくんでいたが、やがて、無言で、びくりとからだを二つ折りに折って机に両手をつき、頭を垂れた。長い髪の毛がばらばらと崩れ落ちて来た。しかし、それも一瞬のことで、本も何も机の上に放り出して廊下へとび出して行った。人気のない廊下に、高い靴音が、うつろに響いた。
「何だどうしたんだ!」
・と学生の一人が甲高く叫んだが、誰も何も言わなかった。言わなくても、事態はすでに明瞭だった。
(堀田善衛「若き日の詩人たちの肖像」)
1936(昭和11)年に法学部政治学科の「予科」に入学した芥川賞作家の堀田善衛(よしえ、1918年~1998年)は、戦後に発表した自伝的小説「若き詩人たちの肖像」(1968年)で、予科の教室内で起こったある日の出来事をこのように描写しています。
作者の分身を思わせる主人公“若者”の同級生だった2人は映画研究会の主要メンバー。小さな雑誌にフランス映画の「どうみてもこじつけの多い解釈をほどこした論文」を書いていたことに目を付けられたのか、“思想犯”として警察に連行され、うち1人は「警視庁の地下室で殺されていた」とあります。
マルクスなどの海外文献を読み漁っていた主人公自身も、下北沢のアパートから突然連行を受けており、新宿にあった淀橋警察署の留置場へ13日間放り込まれた末、取り調べも理由もなく、最後に警察官から殴られたうえで釈放されました。
中学生になった頃に満州事変(1931年)が始まり、戦争のなかった時代は実感が湧かないという主人公が軍隊に召集されるまでを記した本書は、暗い時代に十代を過ごさざるを得なかったやりきれなさが端々に見られます。
北陸の街から上京して日吉の予科に入学した際には丸刈りが強制され、教室では級友が警察によって連れ去られて拷問の末に命まで奪われ、生きていてもいずれは死が間近な戦場へ送られてしまう――そんな時代の日吉キャンパスには現在のような明るさや華やかさは、作品内からも感じられません。
郊外にあった学校の駅を出て、まだ若い銀杏並木のだらだら坂をのぼり、広い、しっとりと濡れた運動場の、誰一人として人影のない観覧席に坐り込んで頭を垂れ、つくづくと若者は考え込んでいた。
(略)
・暗澹として、若者はいつか眠ってしまっていた。前夜一睡もしていなかったのである。眠って、若者は大声で、悲鳴をあげるようにして寝言を言っていた。クラスのぜんぶが大笑いに笑い出した(略)美男子の先生は、前後の野球選手たちが起こそうとするのを制して、
・「寝言を言うほどにくたびれているのなら、起こしても無駄です」
・と言った……。
(堀田善衛「若き日の詩人たちの肖像」)
銀杏(いちょう)並木が巨大といえるサイズに育ったことや、運動場が陸上競技場として立派に改良され、学内には校舎が密集したことを除いては、今も大きくは変わらない日吉キャンパスの描写。
現在の教室内でも頻繁に起きているであろう光景が戦時にも見られたことに少しだけ安堵させられ、時計の針を20年ほど進めて戦後の作品に移ります。
※参考:戦時の日吉キャンパスについては「キャンパスの戦争~慶應日吉1934-1949」(阿久澤武史、2023年)が詳しく、横浜日吉新聞では同書を紹介した記事を2023年6月5日に掲載しています
昭和30年代の教室を描いた石原慎太郎
戦争が終わって10年近くが経過し、古い教育制度の「大学予科」は消え、作品の舞台も高校の教室内に移っていました。
授業が始まって十五分も経(た)つのに何時も時間に几帳面(きちょうめん)な講師は現れなかった。
(略)
・間もなく教頭が級担任の若い体操教室をつれて現れ、担任が、
「これから教頭先生のお話が有るが、このことで諸君の誰かが気のつくことが有ったら何でも言ってくれるように」
・と言い渡した後に重々し気な足どりで教壇に上ると
「実は、大変なことを諸君にお知らせしなくてはならん。この級の宮下嘉津彦君が昨夜又自殺を計った。今度は甚だ重態で医者も見切りをつけている。一体何が原因でこんなことを二度まで彼がしたのか、家の方達も全くわからないと言っておられる。
(略)
・大体こう言うことが一度ならず二度も同じ人の手で行われるということは、全部が全部とは言わぬが諸君等の友情と思い遣(や)り足りないとも言えるのではないか? もし彼が助からなかったならば、諸君にもその責任の幾らかがないとは言えぬと私は思う」
・教頭はそう言い終わるとじろっと皆を見渡した。その顔には死者を悼(いた)むと言うよりは、喫煙を見つけられた学生をつるし上げたり、生徒に残酷な試験の仮処分を言い渡したりする時の、いかにも事件を楽しむといった表情があった。
(石原慎太郎「灰色の教室」)
作者の弟で、のちに昭和のスターとなる石原裕次郎の慶應高校時代をモデルにしたという1954(昭和29)年発表の「灰色の教室」は、芥川賞作家・石原慎太郎(1932年~2022年)の処女作。一大ベストセラーとなった「太陽の季節」(1955年)の単行本・文庫本に収められました。
戦時はよく分からない理由をでっち上げられて国家権力に命さえも奪われ、日本が豊かになりつつあった戦後10年の時点では、不明確な理由で自ら命を絶とうとする10代後半の学徒。
日吉の小さな教室のなかでさえ、時代の急激な変化に翻弄されていたことに堀田善衛と石原慎太郎の両作品からは気付かされます。
湘南高校(藤沢市)から一橋大学と名門国公立校を歩んだ作者の石原慎太郎は、「人々はK学園に最も都会風で先端的な学風をおしつけていたし、学生達もあえてそれに甘んじ、努めてそれを粧(よそお)った」と“K学園”こと当時の慶應義塾に皮肉を込め、終始批判的な眼で処女作の短編を展開しています。
・ハイスクールの校長は、入学式など式典の折々、「なだらかなこの丘陵の上に連なる、これら我が学園の偉容は、本学園をして世評の言う、その洗練さのシンボルであり、我が校の偉大なる内容を語って余りある」とは言ったが、戦時中にほどこされた、黒いダンダラのカモフラージュが、未(ま)だ塗りつぶされずにはげかかって残っているところは、確かにK学園の洗練された無感覚さであり、このやたらに大きなコンクリートの建物は、成り金の勝手口に見かける、馬鹿気(ばかげ)て大きなセメントの芥溜(ごみた)めの大きさであった。
(石原慎太郎「灰色の教室」)
90年の歴史を刻んだ日吉キャンパスを代表する「第一校舎」は、現在でこそ歴史的建造物として認識されていますが、「灰色の教室」が書かれた当時はまだ築20年ほどの新しい校舎。戦中の爆撃を避けるためのカモフラージュに加え、米軍に接収された際の痕跡も残っていたのかもしれません。
この校舎に対しては、湘南の町がなけなしの予算でつくった中学校の小っぽけなロッジ建築のほうがよっぽど粋であるとか、丘陵の線がくっきり浮かぶ上に巨大なタイプライターの活字のようなグロテスクな校舎が乗っているのを見て吐き気に近いものに襲われたとか、散々な書きっぷりです。
また、授業をさぼって入り浸る日吉駅前の麻雀店など教室内外での遊戯にばかり真剣さを見せる生徒の様子や、そうした教え子を放置気味にして職務を遂行する教員らの描写は、作者の皮肉として割り引いて見る必要はありそうですが、昭和30年代初頭のどこか微笑ましい日吉キャンパスの一風景が作品内に凝縮されている点は見どころといえます。
※参考:「灰色の教室」については横浜日吉新聞で2018年6月25日に公開した「<日吉本・綱島本紹介>慶應時代に日吉で過ごした“裕次郎”を描いた石原慎太郎作品」で詳しく取り上げました
芥川賞作品に登場した日吉駅前の風景
石原慎太郎による「灰色の教室」から半世紀超、日吉を舞台に忽然と現れた作品が遠野遥(はるか=男性、1991年~)による「破局」(初出2020年)でした。
遠野はこの作品で2020年上半期の芥川賞を受賞しており、日吉の街や日吉キャンパスが登場する芥川賞作品は今のところ他に見当たりません。
会場は日吉キャンパスの、普段は講義で使われている教室だった。日吉には一年前まで住んでいた。三年に上がるとキャンパスが日吉から三田に変わるので、それで三田に引っ越した。単位を取り損ねた人間は三年になっても日吉に通うけれど、私は単位を落とさなかったから用はなかった。
(遠野遥「破局」)
公立高校から慶應大学法学部に入学し4年生を迎えた主人公の「陽介」は、間近に公務員試験を控えるなか、同級生の「膝」から最後のお笑いライブを見に来てくれと誘われ、その会場で隣の席に座っていた商学部1年生の「灯(あかり)」と知り合ったことで、物語が進んでいきます。
大学の一般教養課程やサークル活動の場としての日吉キャンパスを舞台としている点が前の2作品とは異なるところで、大学生の自由さゆえか学内よりも学外の風景が頻繁に登場します。
「ねえ、これってなんですか?」
・改札の前には銀色の玉のようなオブジェがあって、灯はそれを指差していた。これはぎんだまだと教えてやると、灯は少し笑った。
「名前は聞いたことあるんですけど、何を意味しているのかなって」
・灯の疑問に私は答えられなかった。意味なんてわからないし、考えたこともない。左手で灯の頭を軽く押さえ、右手で髪の毛をゆっくりすいた。指先に挟んだ小さなゴミを風に流すと、灯は恥ずかしそうに笑った。
(遠野遥「破局」)
滋賀県から日吉に引っ越してきたばかりだという新入生・灯が住んだ駅から歩いて10分ほどのアパートや、キャンパスから見て駅の反対側に位置する“屋外に席のあるカフェ”が作中の重要なシーンで現れます。
作中では「ファーストキッチン」という具体的な店名の記載もあり、地元民や慶應関係者は、ぼんやりと駅前商店街の「浜銀通り」あたりを想像し、読み進めることになるはずです。
・約束の時間より早めに着いたはずだったが、灯は既にぎんだまの隣に立っていた。灯とぎんだまの間には妙に打ち解けた雰囲気があり、まるで幼馴染のようだ。
(略)
・灯を店まで案内し、予約しておいたカウンター席に着いた。日吉に住んでいた頃、気になってはいたものの、結局一度も行かなかったパスタ屋だった。しかし、二年も住んで行かなかったのだから、気になってなどいなかったのかもしれない。
(遠野遥「破局」)
最近といえる時期に発表された本作は、堀田善衛や石原慎太郎の作品に流れる時代が醸し出す暗さのようなものを感じさせない一方、主人公の発する言葉や行動を客観視しすぎるゆえの虚無感は、前2作と同様に文学作品ならではといえそう。
“ぎんだま”の意味や駅前のパスタ屋が気になっていたかどうかなど、深く考えなかったことを打ち明けなくても物語自体は進むはずですが、後の展開を暗示する内容も時おり散りばめながら主人公はすべての行動を掘り下げていきます。
そして、日吉のアパートが「事故物件」だったと告白した頃から灯の若干不思議で大胆な行動にも磨きがかかり、主人公の心も身体も揺らぎながら、駅前でのラストシーンにつながります。
遠野遥のデビュー作とされる「改良」(2019年)や最近の「教育」(2021年)、「浮遊」(2022年)では具体的に想像するのが難しい場所を舞台に選んでいることを考えると、「破局」では作者自身が慶應法学部に通った4年間の見聞が生かされている様子でした。
日吉の街ではよく見かける大学生の一般的な行動様式やキャンパス付近の風景が盛り込まれた「破局」は、後の世では読者にどのような思いを抱かせるのでしょうか。
ぎんだまと呼ばれる“虚球自像(こきゅうじぞう)”という名のオブジェに「一体何なのか」と頭を軽く悩ませているのかもしれませんし、石原慎太郎作品に登場した雀荘(麻雀店)やビリヤード場が現在は駅前からほぼ消えたように、パスタ屋やカフェがどうなっているのかも興味深いところです。
安岡章太郎が振り返るキャンパス模様
堀田善衛、石原慎太郎、遠野遥と芥川賞作家が紡いだ“慶應日吉三部作”に加え、忘れてはならないのが堀田と同時代に慶應予科で学び、のちに芥川賞も受賞した安岡章太郎(1920年~2013年)です。
安岡が昭和末期に完結させた「僕の昭和史」(1984年~1988年)は、堀田が作品中に詳しく描かなかった戦中戦後の日吉キャンパスの様子を記憶をたどって記録的に残しており、創作的な要素は薄いため、歴史を追ううえではこちらのほうが有益といえます。
僕は健康状態を心配するよりも、あと三箇月ほどでやってくる再招集の日まで、束の間の自由な時間を愉(たの)しみたかった。復学手続きをとるために大学へも行ってみたが、日吉の校舎は海軍の連合艦隊とかになっており、校庭では白い作業衣をきた水兵たちが、大勢で体操だの手旗信号だのをやっていた。そして僕は、そんな連中を見ていると自分が脱走兵であって、いまにも衛兵に後から襟元をつかんで引き廻されるのではないかという気がして落ち着かず、復学手続きはそのままにして逃げるように学校をはなれた。
(安岡章太郎「僕の昭和史」)
安岡は歩兵隊として派遣された満州(現中国東北部)とソ連(現ロシア)国境の街で胸の病気に襲われ、劣悪な環境下に置かれた大阪の病院や金沢を経た末に一時退役が命じられます。
東京へ戻って焼け残った親類の家々を転々としていたなか、日吉を訪れた際の文章が上記の引用です。
敗戦の1カ月ほど前となる1945(昭和20)年7月ごろの安岡の思い出からは、もはやキャンパスは大学として機能していなかったことがうかがえ、実際にキャンパスの地下や箕輪町あたりでは密かに「海軍司令部」の地下壕が拡張され続けている頃でした。
慶應大学でも起こった学生運動
もう一人、1960年代中ごろの日吉キャンパスを描写していたのが、慶應高校に通った作詞家の松本隆(1949年~)です。
松本は、1970年代の著名ロックバンド「はっぴいえんど」でのミュージシャン活動を経て作詞家活動に軸足を移し、1980年代から90年代にかけて歌謡界で多くのヒット作を生み出しました。そんななか、1986(昭和61)年に発表した小説が「微熱少年」です。
「もうじき大学がストに突入するらしいぜ。高校の俺たちには関係ないっていえば関係ないけどね。珍しいだろ。この大学がそんなことするなんてさ」浅井はカレーを口にほおばりながら言った。
(略)
「授業料値上げ反対だってさ」
「このブルジョア大学がね」
「ムーブメントがしたいんだろう。時代がそういう方向に傾いているからね。口実があればいいんだよ」
(松本隆「微熱少年」)
作品中に日吉キャンパスや高校内が登場する場面はそれほど多くはないのですが、附属高校生ならではの感覚で、1960年代を物語る貴重な描写が作品に残されました。
いずれは自身も進学することになる主人公らが「このブルジョア大学がね」と軽い皮肉を込めながらも意外性を感じ、世間からも驚かれた慶應大学の学生による日吉キャンパスの封鎖は、1965(昭和40)年に行われたものです。
安岡章太郎は週刊誌の依頼でキャンパス封鎖の模様をルポしており、日吉の正門前でバリケードをつくっている学生らにストライキの理由を尋ね、「これをひと言でいえば、国立大と私立大の差別を何とかしてくれ、ということだろう」などと分析したうえで、慶應大学における象徴的な“学生運動”の結末までを「僕の昭和史」に書き残しました。
松本隆作品以降、1970年代から遠野遥の作品が世に出る2020年代まで、半世紀の空白期間はありますが、戦時・戦後・学生運動そして現代と描いた5人の作品からは、90年間におよぶ日吉キャンパスの歩みを生徒・学生の目線からたどることができるはずです。
大倉山の作品にも日吉キャンパス
これまでに紹介した5冊のほか、大倉山を舞台に戦争をテーマとした作品でも、日吉キャンパスに触れている場面がみられます。
劇作家・演出家の久保栄(1900年~1958年)が1953(昭和28)年に発表した「日本の気象」は、海軍気象部が戦時に“疎開”した大倉精神文化研究所(大倉山記念館)で、降伏後間もない頃の場面から始まる戯曲。
大倉山に勤務していた海軍気象部の何人かが敗戦に血迷い、日吉にある海軍の連合艦隊司令部(日吉キャンパス)へ立て籠もるそうだ、といったセリフが出てきます。
2006(平成18)年から2010(平成22)年まで少年誌に連載された漫画「夏のあらし(全8巻)」(小林尽)は、横浜大空襲時からタイムリープ(過去や未来に移動)した“大倉山高等女学校(架空)”の嵐山小夜子が主人公。6巻では「大倉山近くの慶應大には地下に海軍の司令部跡があってね…」と登場人物がさりげなく日吉台地下壕(ごう)を解説するコマが盛り込まれていました。
なお、作者の小林尽は戦争を題材とした本作で、舞台に横浜を選んだのは日吉に海軍の総司令部があり馴染みもあったからと「夏のあらし!コミックガイド6.5」(2009年、スクウェア・エニックス)のなかでコメントしています。
社会学者・作家の古市憲寿(のりとし)が2022年に発表した小説「ヒノマル」は、大倉山をイメージした「観音山」が舞台。
主人公である“軍国少年”の兄が慶應大学の本科に在学中という設定で、日吉キャンパスに勤務する教員についての話をしているシーンが見られます。この主人公の兄は物語内で重要な存在に位置付けられています。
これら大倉山が舞台となる作品は本連載の「第3回」で別途紹介しています。
今回紹介した書誌の詳細
(※)書誌詳細やリンク先は2024年6月時点のものです。入手困難な書誌に限り図書館の書籍案内ページにリンクしました
- 若き日の詩人たちの肖像(堀田善衛):初出1966(昭和41)年~1968(昭和43)年雑誌連載。1977(昭和52)年集英社文庫(上・下巻)、本稿は同社文庫2019年10月発行の第9刷を引用した【出版社ほか入手容易・デジタル版有/横浜市図書館貸出有】
- 灰色の教室(石原慎太郎):初出1954(昭和29)年。1956(昭和31)年新潮社「太陽の季節」(単行本)所収、1957(昭和32)年新潮文庫版「太陽の季節」所収。本稿は同社文庫2011(平成23)年1月発行の68刷改版を引用した【出版社ほか入手容易・デジタル版有/横浜市図書館貸出有】
- 破局(遠野遥):初出2020年「文藝」夏季号。2020年河出書房新社(単行本)、2022年河出文庫版。本稿は河出書房新社(単行本)の2020年8月発行5刷を引用した【出版社ほか入手容易・デジタル版有/横浜市図書館貸出有】
- 僕の昭和史(安岡章太郎):初出1984(昭和59)年講談社「僕の昭和史1」「僕の昭和史2」、1988(昭和63)年「僕の昭和史3」。2005(平成17)年8月新潮文庫版、2018年8月講談社文芸文庫版。本稿は新潮文庫版(初版)を引用した【出版社ほか入手容易・デジタル版有/横浜市図書館貸出有】
- 微熱少年(松本隆):初出1985(昭和60)年新潮社(単行本)。1988(昭和63)年新潮文庫版、2016(平成28)年立東舎文庫版、本稿は1989(平成元)年8月新潮文庫版二刷を引用した【出版社(立東舎)在庫不明・デジタル版有/横浜市図書館(新潮版・立東版)貸出有】
<関連書籍>
- 日本の気象(戯曲)(久保栄):1953(昭和28)年新潮社(単行本)。1962(昭和37)年三一書房「久保栄全集(第4巻)」所収、2008(平成20)年影書房版、本稿は新潮社(単行本)の1953(昭和28)年6月発行初版を参照した【出版社(影書房)在庫不明/横浜市図書館(影書房版・久保栄全集第4巻)貸出有/国会図書館デジタルで久保栄全集第4巻を公開】
- 夏のあらし(全8巻、漫画)(小林尽):初出2006(平成18)年~2010(平成22)年スクウェア・エニックス「月刊ガンガンWING」「月刊ガンガンJOKER」連載、2007(平成19)年~2010(平成22)年スクウェア・エニックス(単行本)。本稿は2009(平成21)年9月発行の第6巻初版を参照した【出版社ほか入手可能・デジタル版有/横浜市図書館貸出有・港北図書館所蔵】
- ヒノマル(古市憲寿):2022年文藝春秋(単行本)。本稿は2022年2月発行の文藝春秋(単行本)1刷を参照した【出版社ほか入手容易・デジタル版有/横浜市図書館貸出有・港北図書館所蔵】
(※)この記事は「横浜日吉新聞」「新横浜新聞~しんよこ新聞」の共通記事です
【関連記事】
・<港北舞台の文芸作品5>農村から学園都市へ、文化人と戦火の日吉台【戦前編】(2025年2月21日)※リンク追記
・<日吉本・綱島本紹介>慶應時代に日吉で過ごした“裕次郎”を描いた石原慎太郎作品(2018年6月25日)
・日吉最古の校舎が伝える「キャンパスの戦争」、慶應塾高・阿久澤さんが歴史本(2023年6月5日)
・連載「港北が舞台の文芸作品」の一覧(2024年6月~)