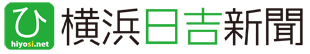鶴見川流域にある自治体などが一体となり、さらなる対策を進めます。鶴見川に関わる1都1県と4市、国土交通省関東地方整備局で組織した「鶴見川流域水協議会」(事務局:国交省京浜河川事務所)は、今週(2022年)2月11日(金・祝)に「鶴見川流域治水WEBシンポジウム~流域治水時代の水マスタープラン」を開きます。
鶴見川の治水にあたっては、上流の東京都町田市から下流の横浜市鶴見区まで、関係する1都1県(東京都・神奈川県)と4市(横浜市・川崎市・町田市・町田市・稲城市)、国交省関東地方整備局が「鶴見川流域水協議会(水協議会)」を組織。
2004(平成16)年8月には対策の基本となる「鶴見川流域水マスタープラン」を策定し、以来、この水マスタープランに沿って、20年近くにわたってさまざまな治水が進められてきました。
近年は日本各地で気候変動による災害が激甚化していることから、河川の区域単位ではなく、鶴見川のように流域全体で対策を行う「流域治水」の重要性を国全体で共有。
昨年(2022年)3月には全国に109ある一級河川と12の二級河川ごとに関係自治体などが集まり、「流域治水プロジェクト」を策定しています。
こうした動きに先行する形で、古くから流域単位での対策に取り組んできた鶴見川でも、あらためて「鶴見川水系流域治水プロジェクト」を昨年3月にまとめました。
今回のシンポジウムでは、全国に先駆けて1980年代から鶴見川の流域全体で治水に取り組んできた関係者が集まり、これまでと今後を語る内容となっています。
当日は、「流域思考」を40年以上にわたって提唱し続けてきた慶應義塾大学の岸由二名誉教授をはじめ、鶴見川流域水委員会で委員長をつとめる虫明功臣(むしあけかつみ)東京大学名誉教授、国交省京浜河川事務所の竹田正彦所長の3氏が登壇。「流域治水時代の水マスタープラン」とのテーマでトークセッションも予定されています。
シンポジウムは今週2月11日(金・祝)の14時からWeb会議システム「Zoom(ズーム)」を通じて開かれ、誰でも視聴が可能。希望者は、「tsurumi@mcp.co.jp」へ「鶴見川流域治水WEBシンポジウム」の件名で名前と返信用メールアドレスを記載のうえ送信し、視聴用のアドレスを入手する必要があります。
なお、応募締め切りは2月9日(水)23時59分までとのことです。
【関連記事】
・鶴見川流域の住民は「水害」にどう立ち向かったか、100年をひも解く貴重な機会(2021年11月18日)
・<コラム流域思考>温暖化時代の危機はすぐそこに、“流域思考”を鶴見川から育もう(2017年6月2日)
【参考リンク】
・2月11日(金)13:30~16:30「令和3年度 鶴見川流域治水WEBシンポジウム開催告知」(ページ下部)
・鶴見川流域治水対策プロジェクトについて(国土交通省京浜河川事務所)