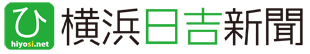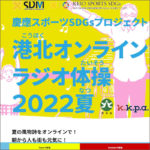スポーツが「SDGs(エスディージーズ=持続可能な開発目標)」に果たす役割について、世界的なスポーツの現場や学術的な視点から考える貴重な機会となりそうです。
慶應義塾大学のスポーツ医学研究センターなどは今週(2022年)3月5日(土)に大型シンポジウム「KEIO SPORTS SDGs(慶應スポーツSDGs)シンポジウム2022」をオンラインで開きます。
慶應大学では、日吉キャンパス内に拠点を置くスポーツ医学研究センターや、大学院システムデザイン・マネジメント研究科(SDM)、体育研究所などの研究者らが中心となり、「スポーツの力を活用し、SDGsの達成に貢献する」との目標を掲げた横断型プロジェクト「KEIO Sports SDGs」を2019年から設置。
日吉キャンパスで行われた東京2020オリンピック・パラリンピックにおける「英国代表チーム事前キャンプ」への支援をはじめ、2021年度には神奈川県の「大学発・事業提案制度」に採択されており、県と連携したオンラインラジオ体操などの地域イベントも開いています。
今回のシンポジウムでは、英国中部にあるシェフィールドで行われている身体活動を増やすための取り組み「Move More(ムーブモア)」を現地から解説する特別講演を皮切りに、5つのセッションを予定。
まずは、「KEIO Sports SDGs」の活動についての全体像をスポーツ医学研究センター・大学院健康マネジメント研究科の小熊祐子准教授が紹介します。
続いて「オリンピック・パラリンピックレガシーとSDGs」のセッションでは、スポーツ医学研究センター・健康マネジメント研究科の石田浩之教授と体育研究所の稲見崇孝専任講師、SFC研究所の佐々木剛二上席所員がそれぞれ昨年夏の「東京2020大会」をテーマに、事前キャンプ受け入れの経験を踏まえたレガシーやSDGsとの関係を語ります。
大学院システムデザイン・マネジメント研究科の神武直彦教授と同研究科の和田康二特任助教は、「システムズアプローチとスポーツSDGs」とのテーマを掲げ、港北区内を含めた神奈川県内で行っている「スポーツSDGsプロジェクト」の実例を報告。
最後のセッションは「GAPPAと地域で実践するスポーツSDGs」と題して小熊准教授とスポーツ医学研究センターの伊藤智也研究員が登壇し、WHO(世界保健機関)が発表した身体活動に関する世界行動計画「GAPPA(Global Action Plan on Physical Activity 2018-2030)」を日本語化するなど普及に注力してきた経験を踏まえ、国内での実践例として藤沢市のケースを紹介する予定です。
シンポジウムは今週3月5日(土)の13時から17時まで、配信はオンライン会議システム「Zoom(ズーム)」または動画配信サイト「YouTube」を通じて行われ、参加(聴講)は無料。事前に申し込みを行い、当日アクセスするURLを取得する必要があります。
【関連記事】
・冬こそ“港北発”のオンライン「ラジオ体操」を、県と慶應が1/6(木)まで6日間(新横浜新聞~しんよこ新聞、2021年12月24日、「KEIO Sports SDGs」の活動)
・新常態での「持続可能なスポーツ」とは、慶應が8/18(火)にオンラインでシンポ(2020年8月6日、シンポジウムは2年前にも開催)
【参考リンク】
・KEIO SPORTS SDGs公式サイト ※SNSへのリンクも
・2022年3月5日(土)オンライン開催「KEIO SPORTS SDGs シンポジウム2022」の案内と申し込みページ(peatix)
・「KEIO SPORTS SDGsシンポジウム2022」のオンライン開催(3/5)(慶應義塾大学、シンポジウムの詳細)