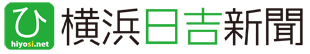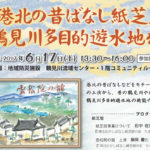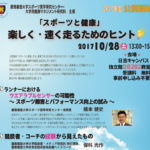港北区の歴史に触れながら、鶴見川の水害対策をリモートで学べます。小机町の地域防災施設「鶴見川流域センター」は、今週(2020年)9月19日(土)午後に講演会「『港北の昔ばなし紙芝居』から流域思考で水害を考える」を同館内で開くのに合わせ、オンライン会議システム「Zoom(ズーム)」による同時配信を行います。

9月19日(土)午後に開かれる講演会「『港北の昔ばなし紙芝居』から流域思考で水害を考える」のチラシ(鶴見川流域ネットワーキングの案内ページより)
今回の講演会では、鶴見川の水害対策を専門家による解説によって学べるだけでなく、港北区に伝わる昔話を題材とした「紙芝居」の上演も行われるのが特徴で、小学生から大人まで幅広い年代に伝える内容になっているといいます。
当日は13時30分から30分間にわたり、区内イベントで紙芝居の上演経験を多数持つ「港北昔ばなし紙芝居の会たまてばこ」の経験豊富なメンバーが登壇。
小机城とともに歴史を重ねてきた古刹(こさつ)「雲松院(うんしょういん)」に伝わる昔話を伝える作品「雲松院の龍」をはじめ、新羽町や大曽根に伝わる伝統行事の由来となった昔話を描いた「大蛇とはやりやまい」、鶴見川が重要な輸送ルートとなっていた過去を伝える「舟運(しゅううん)~ゆめをはこぶふね」の3作品が上演され、紙芝居で鶴見川周辺の昔を感じることができます。
紙芝居に続いて14時から15時30分までは、慶應大学名誉教授で、鶴見川近くで生まれ育った研究者の岸由二(ゆうじ)さんが「流域思考で水害を考える」と題して講演。
小さな水源から鶴見川が形づくられていく上流から、新横浜や綱島などの港北区内を経て、東京湾に注ぐ下流まで、鶴見川とともに暮らす流域全体を俯瞰(ふかん)しながら、水害対策の現状とあり方を解説します。
Zoomでのリモート参加は無料。事前にメールなどで申し込むと、詳細の案内が送られるとのことです。なお、現地で受講する場合も無料ですが、感染対策のため定員が15人までとなっており、事前の申し込みとともに、当日は健康状態のチェックシート提出が必要です。
【関連記事】
・<コラム流域思考>暴れ川だった「鶴見川」の記憶、未来にそなえる流域思考の連携へ(2017年5月1日、岸由二さんによるコラム)
・鶴見川と人生を歩む岸由二さん、日吉や綱島から流域の魅力を伝え続けて四半世紀(2016年8月15日)
【参考リンク】
・9月19日(土)「港北の昔ばなし紙芝居」から流域思考で水害を考える 開催(鶴見川流域ネットワーキング、PDFに申し込み書や詳細案内)