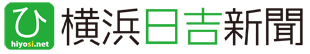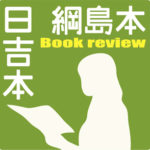昨日2016年9月25日(日)付け「神奈川新聞」の7面日曜版に60年以上前の日吉の古い写真5枚と、その頃の様子を伝える貴重な特集記事が掲載されています。

2016年9月25日(日)付け「神奈川新聞」の7面日曜版に掲載された「モノクロームのころ 写真が記録したまち」
これは「モノクロームのころ 写真が記録したまち」というコーナーの第38回目に日吉が取り上げられたもので、神奈川新聞が撮影した報道写真のなかから過去の日吉駅や街並みなどの写真とともに、日吉の歴史についても触れていました。
高台にある日吉公園(日吉2)付近から撮影した1952(昭和27)年のパノラマ写真をはじめ、「駅は東横線きってのスマートさ」と同新聞が評したモダニズム建築の駅舎写真(1952年)、日吉駅西口の高台から撮影されたとみられる同年の写真では、驚くほど緑が多い日吉本町1~2丁目付近の住宅街と日吉台小学校が写されています。
これら写真の記事では「牌の音も響く?丘の上の田園都市」とのタイトルで、当時神奈川新聞に連載された「新相模風土記」というコーナーの1952年7月掲載「日吉編」を引用をしながら、日吉の歴史を概説。
慶應義塾大学ができたことで「学生相手の娯楽場や喫茶、食堂、本屋や洋服屋がわれ先にと馳(は)せ参じ」「現在では麻雀(マージャン)屋十六軒、玉突屋二軒などはいずれも繁盛」「ポン、カンと威勢のよいパイの音が朝から響き」「いつの間にか俗っぽい場末町に変わってしまった」(新相模風土記)・・・など、今では考えられないような当時の「なんとも退廃的な雰囲気」(記事)をふり返っています。
現在のラーメン屋と同じくらいの数の麻雀屋(雀荘=じゃんそう)があった、というのも想像がつかない光景です。
残念ながらこのコーナーは、紙の新聞にしか掲載されていないようでインターネット上では見ることができません。新聞販売店で9月25日(日)の神奈川新聞を購入するか、図書館などでぜひご覧ください。
1950年代は石原裕次郎さんが日吉へ通っていた頃
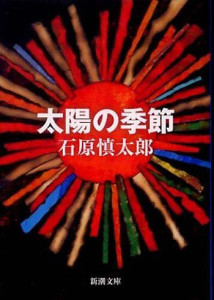
1950年ごろの日吉を知るには石原裕次郎さんをモデルに書いたとされる小説『灰色の教室』が最適。文庫版の『太陽の季節』に収録されている
1950年代(昭和26年~)ごろの日吉の風景については、元東京都知事で作家の石原慎太郎さんの処女作『灰色の教室』(1954年12月発表)という作品で頻繁に登場します。
同作品は、石原慎太郎さんの弟で慶應義塾高校(塾高)出身(1951年入学)である石原裕次郎さんをモデルに書いたとされる小説で、フィクションを交えながら、塾高内外での“退廃的”な様子が多々描写されており、当時の日吉を知るには絶好の作品です。同作品は新潮文庫刊の『太陽の季節』に収録されているため、手に入りやすいのも利点です。
続く1960年(昭和35年~)代の日吉を知るには、作詞家で塾高出身である松本隆さんの小説『微熱少年』(新潮社、1985年)が適しています。60年代になると、作品における日吉の風景描写にも、どこか虚無感のようなものを感じるようになるはずです。
『微熱少年』は新潮文庫版が長年品切れ状態でしたが、最近になって電子書籍「Kindle(キンドル)版」や立東舎文庫(リット―ミュージック社)版が出たため、手に入りやすくなりました。
昭和の元気だった学生街・日吉を感じるには、上記の2冊がおすすめです。
【関連記事】
・<コラム>自らの利益のため「日吉村」を引き裂いた大都市横浜と川崎の罪(2016年1月3日、戦前の歴史を概説)
・<コラム>引き裂かれた日吉村、次に来たのは大迷惑な日本海軍とアメリカ軍(2016年1月10日、戦中の歴史を概説)
【参考リンク】
・石原慎太郎『太陽の季節』についての紹介(新潮社、文庫版に『灰色の教室』も収録)